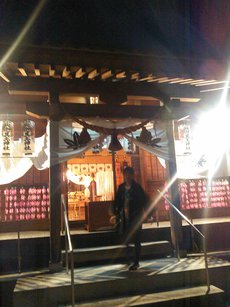2011年09月21日
手筒作成
さて、昨日に続き、急遽参加となった手筒花火製作だが。
自分は途中参加ですんで、いくつかの作業&準備をしておりません。
手筒花火の心材となる竹取りが、一番たいへんらしいです。
(材料確保、選定が)

竹は孟宗竹という種類らしく、肉厚で直径も10cmを越えるものも多い。
3年以上生えている竹は、色がだんだんと茶色(乾燥して)になってくるので、
使用するのは2年物の青竹だ。
自分は途中参加ですんで、いくつかの作業&準備をしておりません。
手筒花火の心材となる竹取りが、一番たいへんらしいです。
(材料確保、選定が)

竹は孟宗竹という種類らしく、肉厚で直径も10cmを越えるものも多い。
3年以上生えている竹は、色がだんだんと茶色(乾燥して)になってくるので、
使用するのは2年物の青竹だ。
長さは85cm、目印をつけてノコギリで切っていきます。
なるべく真っ直ぐにということで慎重に。

お次は、こんな手作りの専用道具で節を抜いていきます。
鉄の棒にヤスリを溶接したものです。

この節抜きが成否に関わってくるらしいので、慎重に行います。
成否=生死ですから!?

大まかに削って、ここからはコツコツと。
派手な花火に対して、とても地味な作業です。

みなさん、黙々と小突いてます。
そんなこんなで、約2時間。
最後にペーパーかけて、仕上げて節抜き完了。

下地として麻袋を巻きつけて固定。

縄を巻きはじめる上部を固定するための針金を取り付け。
ここからグルグルと縄を巻いていく作業をしていきます。

昔は当然、手作業だったらしいんだけど・・・
現在は文明の利器というものがありまして(笑)

こだわって、手巻きという方もみえますがね。
均一なテンションをかけられるという点では、こちらの方が安全か。

手筒は2回巻くようで、下巻き後にゴザを巻いたあとに、また縄を巻きます。
同じように上部の固定から。

注意点はたくさんありますが、
難しいポイントは、この針金の編み込みかな。

セッティングを完了して、機械が空くのを待ちます。
で、完成したのがコチラ

ごくごく、オーソドックスな形ですが、最初ということで。
何十回とやってる方々は、巻き方、取っ手の付け方などここからカスタマイズするみたいです。

ま、初めてにしちゃあ、まずまずなんでね?
ひとまずの行程としては終了であります。
来週に続く。
なるべく真っ直ぐにということで慎重に。

お次は、こんな手作りの専用道具で節を抜いていきます。
鉄の棒にヤスリを溶接したものです。

この節抜きが成否に関わってくるらしいので、慎重に行います。
成否=生死ですから!?

大まかに削って、ここからはコツコツと。
派手な花火に対して、とても地味な作業です。

みなさん、黙々と小突いてます。
そんなこんなで、約2時間。
最後にペーパーかけて、仕上げて節抜き完了。

下地として麻袋を巻きつけて固定。

縄を巻きはじめる上部を固定するための針金を取り付け。
ここからグルグルと縄を巻いていく作業をしていきます。

昔は当然、手作業だったらしいんだけど・・・
現在は文明の利器というものがありまして(笑)

こだわって、手巻きという方もみえますがね。
均一なテンションをかけられるという点では、こちらの方が安全か。

手筒は2回巻くようで、下巻き後にゴザを巻いたあとに、また縄を巻きます。
同じように上部の固定から。

注意点はたくさんありますが、
難しいポイントは、この針金の編み込みかな。

セッティングを完了して、機械が空くのを待ちます。
で、完成したのがコチラ

ごくごく、オーソドックスな形ですが、最初ということで。
何十回とやってる方々は、巻き方、取っ手の付け方などここからカスタマイズするみたいです。

ま、初めてにしちゃあ、まずまずなんでね?
ひとまずの行程としては終了であります。
来週に続く。
タグ :手筒花火
Posted by MORI☆KATSU at 10:11│Comments(0)
│手筒花火